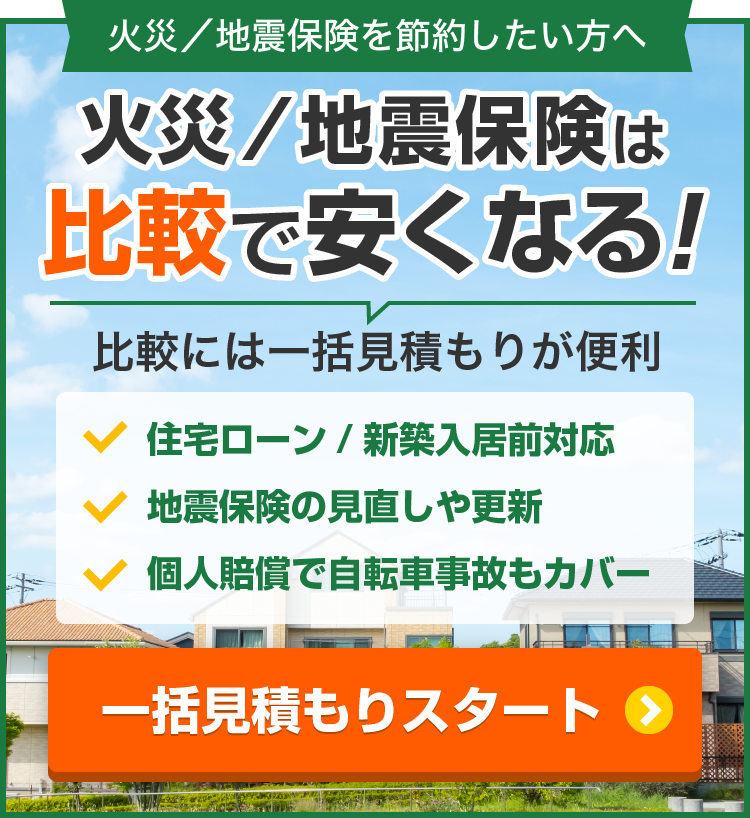火災保険は自動車の自賠責保険のような強制加入の保険ではないので、ローンを借りるための条件に指定されるなどしていなければ、必ず加入しなければいけないということはありません。住宅ローンの返済が終われば、金融機関からの火災保険への加入強制も解除されるので「火災保険に入らない」という選択も可能です。
しかし、火災保険の契約がなければ住宅に対する様々なリスクに自己資金のみで対応していかなければなりません。住宅ローンの返済がない人で火災保険の加入について悩んでいる人は、火災保険に入らないことでどのようなリスクが発生するのか知っておきましょう。
目次
火災保険に入らないリスク
火災保険は、火災だけに備える保険ではありません。住宅に関する様々な損害を補償範囲として含んでおり、近年、増えている自然災害などのリスクにも備えることができます。これまでに災害などがあまり起こらなかった地域では、自然災害リスクも少なく火災保険の契約がなくても大丈夫ではないかと思うこともあるかもしれませんが、大きな被害をもたらす災害は、いつ、どこで起こるか分からないということを考えておく必要があります。
自宅が火災や自然災害で被害を受けた時にどれくらいの損害が発生するかということを、損害保険料率算出機構の「火災保険・地震保険の概況2024年度版」をもとに実際に火災保険で支払われた保険金から考えてみましょう。
事故種別の支払い金額
| 事故種別 | 2021年度 | 2022年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 保険金 | 1件あたり 保険金 | 件数 | 保険金 | 1件あたり 保険金 | |
| 火災、破裂・爆発 | 7,816件 | 36,931百万円 | 4,725千円 | 7,722件 | 36,690百万円 | 4,751千円 |
| 風災・ひょう災 | 116,448件 | 47,566百万円 | 408千円 | 201,304件 | 99,234百万円 | 493千円 |
| 雪災 | 87,062件 | 55,094百万円 | 633千円 | 56,757件 | 29,070百万円 | 512千円 |
| 水災 | 2,555件 | 12,396百万円 | 4,852千円 | 4,749件 | 20,398百万円 | 4,295千円 |
| その他 (水濡れ損害など) | 337,133件 | 81,367百万円 | 241千円 | 375,027件 | 92,822百万円 | 248千円 |
※数字を丸めた際の四捨五入の関係で1件あたりの保険金の数値が表の数値から計算した値とずれが生じている場合があります。
何によって被害を受けたかで大きく金額が異なりますが、火災保険の1件あたりの保険金支払額は数十万~数百万円と自分で支払うには痛い金額となっています。また、被害に備えるという意味では平均額だけでなく、最大でどれくらいの支出が発生しうるかということも考える必要があります。例えば、火災により自宅が全焼してしまうようなケースを想定すると、新たに住宅を取得するための費用について考えておかなければいけません。
自分がどれだけ気を付けていても放火や隣家からのもらい火で火災になってしまう可能性はありますし、自然災害での被害は防ぎきれない場合があります。火災や自然災害で住宅を失っても生活の手段がある、十分な資金があるという場合を除いては火災保険の契約を行っておくことをおすすめします。
もらい火のリスク
日本には「失火責任法」という法律があり、隣家の火事が自分の家に燃え移った場合でも、重大な過失がある場合を除き、火元に損害賠償請求をすることができないということになっています。そのため、他人の家や近くで起こった火災が原因で自分の家も燃えてしまったというような類焼リスクについても自分で備えなければいけません。
どれだけ自分が火災に気を付けていても類焼リスクは避けられない場合があります。自分の過失ではなくても自分の家が火事に巻き込まれてしまった場合は自分の責任として修理を行わなければいけません。そのようなリスクに備えるためにも火災保険は重要です。
賃貸の場合のリスク
賃貸物件を借りる時も火災保険の契約を求められることがほとんどです。賃貸の場合、建物は大家さん、家財は入居者の所有物ですから、家財については入居者が加入する家財保険で補償します。
しかし、ボヤのような火事であっても、自分の所有する家財だけでなく建物にも損害が及んでしまうことが多いでしょう。入居者が借りている部屋で火災や破裂・爆発、水濡れなどを起こし建物に及ぼした損害については、大家さんから損害賠償を求められる場合があります。そのような場合に備えて、賃貸用の火災保険の補償内容には、借家人賠償責任補償が含まれています。借家人賠償責任補償は、火災などにより部屋に損害を与えてしまった場合の大家さんからの損賠賠償請求の費用に備えることができます。
しかし、失火の場合は先ほどの失火責任法により損害賠償請求されないのでは?と思う方もいるのではないでしょうか。少し難しい話になりますが、失火責任法で損害賠償請求ができないというのは民法第709条に定められている「不法行為による損害賠償」、つまりは故意や過失によって生じた損害に対する損害賠償請求です。一方で、借家人には借りた部屋に対して原状回復義務がありますが、火事などでそれが果たせない場合、大家さんは「債務不履行による損害賠償請求」を行えます。債務不履行による損害賠償請求は民法第415条に規定されており、失火責任法の影響は受けないのです。
例え注意していても部屋で火災や破裂・爆発、水濡れなどが起こってしまい建物に損害を及ぼしてしまう可能性はあります。そのような場合の損害賠償リスクに備えて借家人賠償責任保険補償がある火災保険の加入があると安心です。
賃貸の場合の火災保険契約も不動産会社からお勧めされる保険会社に加入しなければいけないという事はありません。自分で選ぶことができますので保険会社を比較し自分に合った火災保険をみつけましょう。
地震のリスクは地震保険で備えましょう
自然災害の中でも地震による被害は、火災保険では補償されません。地震による被害とは、「地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害」といった地震に起因する損害です。これらの補償は火災保険のセットで契約する地震保険で備える必要があります。
日本は地震の多い国です。大きな損害をもたらす大地震は、いつ、どこで起こるか分からないため日ごろの備えが必要です。防災グッズの用意や避難場所の確認などの家庭での準備を十分に行い、地震などで被害を受けた場合の生活の再建費用については、地震保険で備えることを検討しましょう。
地震保険への加入においても火災保険と同様、地震などの被害を受けても生活の手段がある、十分な資金があるという場合を除いては、いつ起こるか分からない地震の被害に備えて契約しておくことをおすすめします。
地震保険の補償内容
地震等による損害を受けた場合は、損害の程度によって補償の判定がされます。全損、大半損、小半損、一部損の認定を行い、その認定に沿った保険金の支払いとなります。保険金額は、契約している火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で決めます。ただし、上限が決まっており、建物は5,000万円、家財は1,000万円です。
建物
| 損害基準 | 保険金支払額 | |
|---|---|---|
| 全損 | 主要構造部の損害額が建物の時価50%以上 | 建物の地震保険の保険金額の全額(時価額が限度) |
| 焼失または流出した床面積が建物の延床面積の70%以上 | ||
| 大半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の40%以上50%未満 | 建物の地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
| 焼失または流出した床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満 | ||
| 小半損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の20%以上40%未満 | 建物の地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
| 焼失または流出した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 | ||
| 一部損 | 主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満 | 建物の地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
| 建物が床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を受け、損害が生じた場合で全損・大半損・小半損に至らないとき |
家財
| 損害基準 | 保険金支払額 | |
|---|---|---|
| 全損 | 損害額が家財全体の時価の80%以上 | 家財の地震保険の保険金額の全額(時価額が限度) |
| 大半損 | 損害額が家財全体の時価の60%以上80%未満 | 家財の地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
| 小半損 | 損害額が家財全体の時価の30%以上60%未満 | 家財の地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
| 一部損 | 損害額が家財全体の時価の10%以上30%未満 | 家財の地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
平成29年1月1日以降始期の地震保険
※地震保険に関する法律施行令の改正(平成29年1月1日施行)により、「半損」が「大半損」および「小半損」に分割されています。
地震保険の補償内容は、建物が全損した場合でも火災保険金額の50%しか補償とならないため、補償の足りない保険のように思えますが、地震による被害は火災保険では補償されません。地震保険で地震による被災後の生活再建の資金を考えましょう。
-

地震保険は必要?
火災保険に入るときに悩むことの一つに地震保険にもセットで加入するべきかということがあります。火災保険だけでは地震による被害は補償されません。どのような人は地震保 ...続きを見る
住宅ローンを組む時は火災保険の契約が必須!
住宅ローンを借りる時には、ほとんどの金融機関で火災保険の契約を必須の条件としています。それは、火災や自然災害で住宅を失うなどした際に、住宅ローンの返済が滞らないようにするためです。
地震保険は火災保険とセットで契約しますが、住宅ローンを組む際の地震保険への加入は任意となっており必須ではありません。しかし、地震が原因で住宅を失っても住宅ローンの返済はなくなりません。自宅が地震によって全損し、地震保険では補償が足りなくても、住宅ローンの返済資金や仮住まいの生活費、自宅の修理費用として地震による被災後の当面の生活費として、地震保険が役立つかもしれません。住宅ローン返済中は、そのようなことも考え、地震保険の契約についても検討しましょう。
-

住宅ローンに火災保険は必須?地震保険にも加入する?
住宅ローンを借りる際に銀行から火災保険の契約を求められることがほとんどです。住宅ローンを借りるのにどうして火災保険の契約が必要なのでしょうか。また、火災保険を契 ...続きを見る
安い保険料で火災保険に契約するために
火災や自然災害など様々な住宅に係るリスクに備えるために火災保険で備えておくことは日々の暮らしの安心にもつながります。万が一のリスクに備えて加入する火災保険は家計への負担を考えても少しでも保険料を安く契約できた方がよいでしょう。火災保険を安く契約するためにはいくつかポイントがありますので確認しておきましょう。
1.複数の保険会社を比較する
火災保険を安く契約するためには複数の保険会社を比較し、同じ補償内容の条件で一番保険料の安い保険会社と契約することです。各保険会社で同じ補償内容であっても保険料に差があります。たくさんある保険会社を比較するには、火災保険の一括見積もりサービスを利用すると便利です。1度の情報入力で複数の保険会社の見積もりを請求することができます。少しでも保険料を安く抑えるために利用してみましょう。
2.不要な補償は外す
火災保険は補償範囲が広くなるほど保険料も高くなります。火災保険は、火災による損害以外にも自然災害による損害や日常のトラブルなど幅広い範囲が補償対象となっています。補償範囲は自分の住環境に合ったベストな内容で備えられるように必要かどうかを取捨選択しましょう。不要だと思う補償を外すことで保険料を抑える事ができます。
3.免責金額を大きくする
火災保険は、免責金額を設定することで保険料を安くすることができます。免責金額とは、自己負担金のことで、住宅に損害があった時の自己負担が大きいほど保険料は安くなります。保険料を安く抑えるために預貯金などで備えられる金額を免責金額で設定しておくとよいでしょう。
-
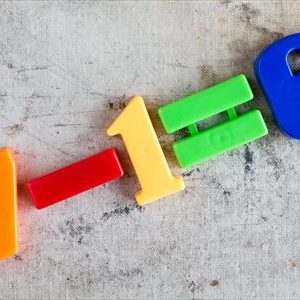
火災保険の免責金額って何?いくらで設定する?
火災保険の契約の際、免責金額を自分で選んで設定する必要がある場合があります。しかし、「免責金額」という言葉は日常生活で使うことはほぼなく、免責金額とはいったい何 ...続きを見る
4.長期契約で一括払いをする
火災保険は最長で5年の長期契約が可能です。火災保険の保険期間を1年で毎年更新する場合と保険期間を1年超の長期契約にする場合では、長期契約にすればするほど保険料の総支払額が安くなります。
また、長期契約は、月払より年払の方が保険料が安く、年払よりも一括払の方が保険料が安いです。年払や一括払では一度に支払う保険料が多くなってしまいますが総支払額で考えると保険料を安く抑えることができます。
-

火災保険の保険期間は最長5年!長期の方がお得?
火災保険の保険期間(契約期間)は最長5年です。火災保険は1年契約で毎年更新していく場合と5年契約する場合とではどちらがお得になるのでしょうか?1年契約と長期契約 ...続きを見る
5.保険会社の割引制度を利用する
保険会社の中には、一定の条件を満たした場合に保険料の割引をする制度を設けているところがあります。例えば、新築割引や築浅割引などは、多くの保険会社で取り扱いがある割引制度です。また、独自のユニークな割引制度を設けている保険会社もあります。複数の保険会社を比較して適用となる割引がないか確認してみましょう。
-

火災保険の割引制度
火災保険や地震保険には保険料を安くすることができる割引制度があります。地震保険は各社共通ですが、火災保険によってはどの割引制度を採用しているのか、また、どの程度 ...続きを見る
まとめ
住宅ローンの返済中は、借入先の条件で火災保険への加入が必須となっていることがほとんどなため、火災保険に契約しないということはないかと思います。しかし、住宅ローンの返済も終わり、火災保険の加入意思を自分で判断しなければいけなくなった時に火災保険の必要性について改めてしっかり考えてみましょう。自分の住宅は自分で守るという意識をもって、万が一大切なマイホームに損害があった時の備えは、「自己資金だけで賄えるか」ということを考えてみましょう。火災保険に「加入しない」というリスクをしっかり理解しておくことが大切です。
内閣府の試算によると火災保険の加入率は、82%です(重複を除いた火災保険・共済保険の加入割合)。火災や自然災害などで住宅が全壊した時の備えを自己資金で賄えるという家庭は少ないでしょう。火災保険の契約があれば様々な住宅に係るリスクに備えておくことができます。火災保険は、保険料を安くするポイントを押さえ、上手に契約しましょう。その場合の保険会社の比較には、火災保険の一括見積もりサービスを利用すると便利ですので利用してみましょう。