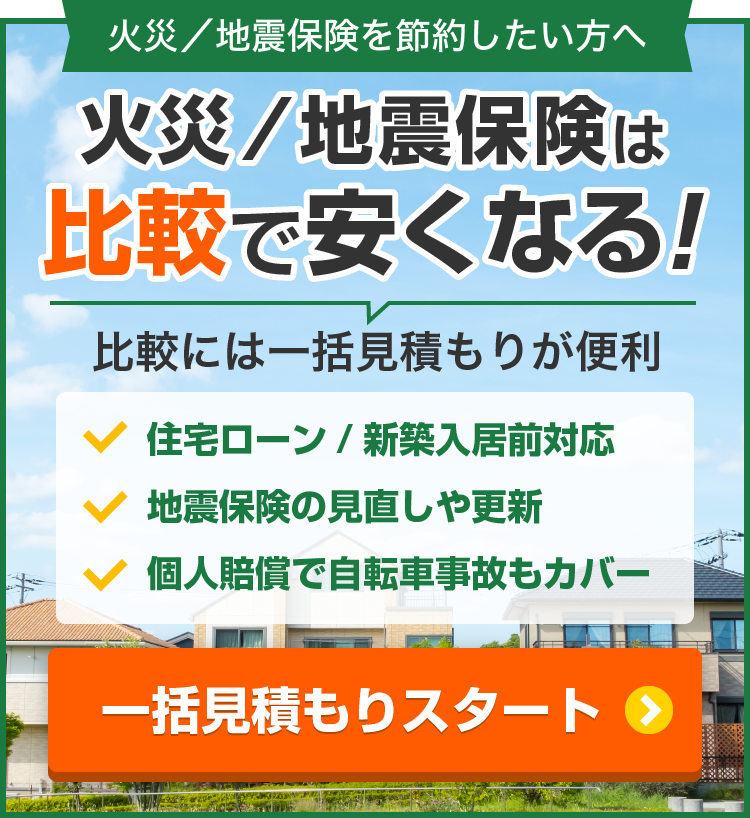火災保険の加入率は共済も含めると82%と推計されています。多くの世帯で加入されている火災保険ですが、「火災なんてめったに起こらないし、保険料の無駄だから必要ないのでは?」と考える方もいるようです。本当に必要ないのか、火災保険の必要性について考えてみます。
火災の発生件数、被害額
実際のところ、1年間でどれくらいの火災が起きていて、火災が起きた場合にどれくらいの被害に遭うのでしょうか?消防庁の令和5年(1月~12月)における火災の状況(確定値)によると、令和5年の1年間での罹災世帯数は18,882世帯です。令和5年1月1日時点の世帯数が60,266,318世帯なので、約3,192世帯に1世帯が罹災していることになります(総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」)。3,192世帯といわれてもピンとこないかもしえませんが、群馬県の下仁田町がこれぐらいの世帯数です。
また、令和5年における建物火災の出火件数は20,974件、損害額は82,040,342千円なので、1件当たりの損害額は約390万円です(令和6年版消防白書_資料編)。
この発生件数、被害額を見て火災保険には入るべきだと感じた人は各保険会社の見積もりを取って検討してみてください。一括見積もりサービスを利用すると一度に見積もりを取れて便利です。必要ない、あるいはよくわからないと感じた人は以下を読み進めて改めて必要性について考えてみてください。
隣家からの延焼でも自分で直す必要がある
自分ではどれだけ気を付けていても、隣家で出火して自宅まで延焼する可能性があります。しかし、日本には「失火責任法」という法律があり、延焼によって自分の家が燃えても、火元となった人に重過失がなければその人に損害賠償請求をすることができません。この法律は明治時代にでき、木造で密集した日本の住宅状況では火元に延焼の責任を負わせるのは困難であるという理由から制定されました。
2016年の糸魚川の大火のように現代の日本でも大規模な延焼が起こる可能性を否定できません。延焼の被害を受けた側としては理不尽に思うかもしれませんが、火元の人に重大な過失がなければ、自分の火災保険を使うか自分の貯蓄などから修繕あるいは再建費用を出す必要があります。
-

失火責任法とは?もらい火の火事は損害賠償請求できない!?
延焼によって損害を受けても火元の人に損害賠償請求ができないという話を聞いたことはありませんか?明治時代にできた「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)という法律 ...続きを見る
また、隣家などで火災が起こり、消火活動による放水で自宅も被害を受けたり、延焼を防ぐためにやむを得ず破壊されたりすることもあります。こうした消防活動による破壊は消防法第29条第1項によって適法と解釈されており、消火や延焼の防止、人命の救助のために必要な場合は消防隊側に補償の責任はなく、損害賠償を請求することはできません。火災保険に加入していれば、自宅や隣家などで行われた消火活動による損害についても補償を受けることができます。
-

火事の消火活動で水浸しに…火災保険で補償される?
火事が起きた場合、建物や家財が燃えることによる損害だけでなく、消火活動によって水濡れや破損などの損害が発生することがあります。また、消火活動による損害は自宅で火 ...続きを見る
火災保険は火災のためだけの保険ではない
火災保険は「火災」保険という名前から火災の時にしか使えないと思っている方もいるようですが、自然災害や盗難、日常のトラブルなど様々な損害を補償範囲に含んでいます。火災にしか使えないと思い込んで必要ないと思っている場合は認識を改める必要があります。
| 損害の種類 | 内容 |
|---|---|
| 火災、破裂・爆発、落雷 | 失火・延焼・ボヤなどの火災、ガス漏れなどによる破損・爆発の損害、落雷による損害を補償。 |
| 風災・雹災・雪災 | 台風等の強風による損害、雹(ひょう)や霰(あられ)による損害、豪雪の際の雪の重み、雪の落下などによる事故または雪崩により生じた損害を補償。 |
| 水災 | 台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどにより生じた損害を補償。 |
| 水濡れ | 給排水設備の故障や他人の戸室で生じた事故による水濡れ損害(水漏れ)を補償。 |
| 物体の落下・飛来・衝突 | 車の飛び込みや飛び石など建物外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより生じた損害を補償。 |
| 盗難 | 家財の盗難や盗難に伴う鍵や窓ガラス等の建物の損害を補償。 |
| 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 集団行動などに伴う暴力行為・破壊行為による損害を補償。 |
| 破損・汚損など | 子どもが室内でボールを投げ、窓ガラスが破損してしまった等、事前に予測して防ぐことができず、突発的な事故によって生じた建物や家財の損害を補償。 |
必要な補償を選択して見積もりが可能!
保険金の支払額の推移をみても、「火災、破裂・爆発」による保険金の支払額よりも「自然災害(風災・雹災・雪災・水災)」での保険金の支払額の方が多い年度が続いています。(火災保険・地震保険の概況(2024年度版))
| 事故種別 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 (件) | 保険金 (百万円) | 件数 (件) | 保険金 (百万円) | 件数 (件) | 保険金 (百万円) | |
| 火災、破裂・爆発 | 7,762 | 35,809 | 7,816 | 36,931 | 7,722 | 36,690 |
| 落雷 | 36,947 | 12,470 | 37,027 | 12,214 | 43,991 | 14,728 |
| 風災・雹災 | 196,418 | 94,417 | 116,448 | 47,566 | 201,304 | 99,234 |
| 雪災 | 78,748 | 45,725 | 87,062 | 55,094 | 56,757 | 29,070 |
| 水災 | 4,444 | 25,196 | 2,555 | 12,396 | 4,749 | 20,398 |
| 水濡れ | 57,693 | 39,202 | 54,298 | 36,546 | 57,098 | 40,352 |
| その他 | 277,111 | 46,363 | 282,835 | 44,820 | 317,929 | 52,470 |
※「件数」および「保険金」は、対象年度に発生した事故に対して当該年度およびその翌年度に支払った件数および保険金を集計したものです。
「その他」は盗難、物体の落下、破損・汚損、電気的・機械的事故および地震火災費用等に対する保険金を集計したものです(不明を含みます)。
出典:損害保険料率算出機構「火災保険・地震保険の概況(2024年度版)」
公的支援だけでは不十分
大きな自然災害の被害を受けた場合、何か公的制度によって補償されるのではないかと思うかもしれません。確かに「被災者生活再建支援制度」という公的支援制度はあるのですが、その支援額は十分な金額とは言えません。受けられる金額は住宅の被害の程度と住宅の再建方法によって異なりますが、最大でも300万円までしか支援を受けられません。
対象世帯
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等の自然災害により
①住宅が「全壊」した世帯
②住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯
⑤住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯
| 基礎支援金 (住宅の被害程度) | 加算支援金 (住宅の再建方法) | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| ①全壊 ②解体 ③長期避難 | 100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
| 補修 | 100万円 | 200万円 | ||
| 賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 150万円 | ||
| ④大規模半壊 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 |
| 補修 | 100万円 | 150万円 | ||
| 賃借(公営住宅を除く) | 50万円 | 100万円 | ||
| ⑤中規模半壊 | - | 建設・購入 | 100万円 | 100万円 |
| 補修 | 50万円 | 50万円 | ||
| 賃借(公営住宅を除く) | 25万円 | 25万円 | ||
※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額
支給されるのは最大でも300万円ですが、その金額では元の住宅と同程度の物件の再購入や再建築は難しいでしょう。自分で火災保険に加入して備えておくことが大切です。
オール電化やマンションでも火災保険は必要?
オール電化住宅やマンションにお住まいの方は一般の戸建ての住宅よりも火災のリスクが低いので火災保険の必要性に疑問を持つ人がより多くいるようです。しかし、先述の通り火災保険は火災のためだけの保険ではなく、自然災害による被害や日常のトラブルなどでも補償を受けることができます。
台風などによる強風や強風による飛来物で窓ガラスが割れてしまったり、マンションの場合は上階からの漏水で水漏れ被害に遭ってしまったりする可能性があります。オール電化住宅においては火を使わなくても、電気機器の漏電など電気を原因として火災が発生する可能性もあります。また、隣家からの延焼や放火も考えられるので火災のリスクがないというわけではありません。
自分の住宅が火災や自然災害によって損害を受けた時に、貯蓄で賄うことができないのであれば火災保険に加入したほうがよいでしょう。
-

オール電化でも火災保険は必要なの?
「オール電化住宅の場合、火を使わないから火災保険はいらないのでは…」と考える人がいるようです。しかし、オール電化住宅であっても火災保険は必要です。なぜオール電化 ...続きを見る
まとめ
火災保険は火災のためだけの保険ではありません。火災に遭う可能性は低くても自然災害によって損害を受ける可能性も考えなくてはいけません。また、延焼により住宅が燃えてしまっても、失火責任法により火元の人に重過失がなければ損害賠償請求ができないことも覚えておきましょう。
住宅の修繕・再建費用は高額になることがあります。貯蓄で賄うことができない場合やその後の生活が大変になるのであれば火災保険に加入しておいた方がよいでしょう。

著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。