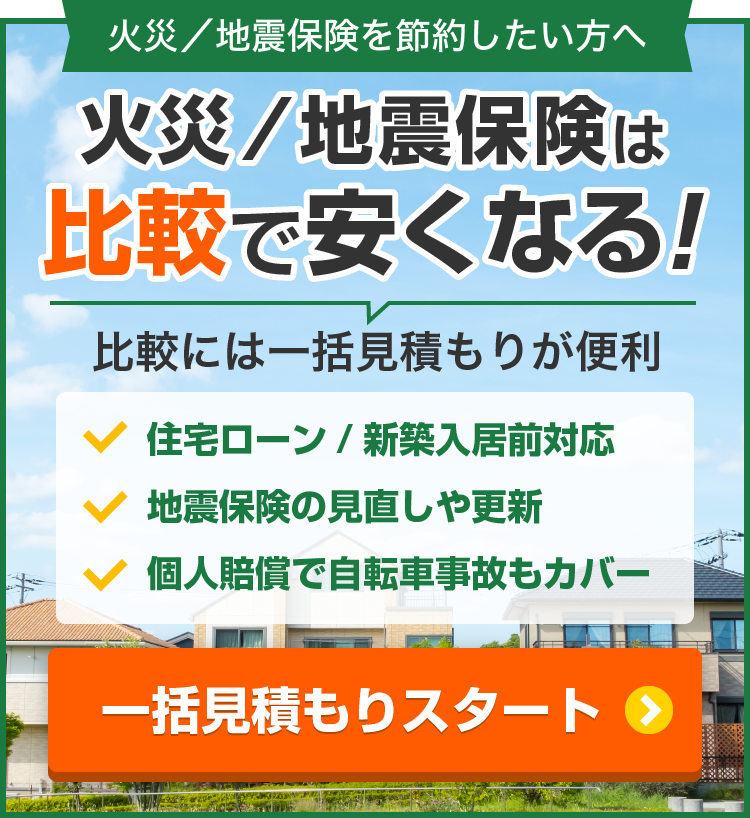住宅を購入したら火災保険の加入が必要です。任意加入の保険ではありますが、住宅というのは多くの人にとってとても大きな買い物です。もし火災や自然災害で住宅を失ってしまったとき、火災保険に入っていなかったらその後の生活が非常に苦しくなってしまうでしょう。それでは住宅の引き渡し日から補償が開始されるようにするにはいつから検討していつまでに申し込めばよいのでしょうか。
火災保険はいつまでに申し込む?
住宅を購入した場合、火災保険の補償開始日は住宅の引き渡し日とするのが普通です。火災保険の申し込みは補償開始日が引き渡し日に間に合うように行います。保険会社にもよりますが、申し込みから補償開始までには各種書類の提出やその内容の確認などで数日かかることがあります。どこの保険会社で火災保険に加入するか決めたらなるべく早めに、2週間前には申し込みを行うようにすると安心です。
また、火災保険の検討は1か月半~2カ月前には開始するのがよいでしょう。各保険会社から見積もりを取って、それが出そろうのには1~2週間見ておくとよいです。そこから、補償内容の吟味や保険会社の比較をじっくりと行うことを考えると、やはり住宅の引き渡し日の1か月半~2カ月前には準備を開始するのがよいと思われます。
保険会社各社の見積もりを取るうえで、一括見積もりサービスを利用すると便利です。1度の入力で複数社の見積もりが取れるので、1社1社個別に同じような内容のことを入力する手間が省けます。各保険会社の見積もり内容を比較して自分に合った火災保険を探しましょう。
住宅ローンとセットで火災保険に加入する場合
住宅ローンを組む場合、火災保険の加入を必須としている金融機関がほとんどです。その理由は、ローン返済中に火災等で住宅を失うなどした際に、ローンの返済が滞らないようにするためです。
金融機関は住宅ローンの融資時に加入する火災保険を紹介する場合があります。しかし、金融機関から勧められる保険会社に必ず入らなければならないということはありません。そして、金融機関が勧める火災保険に入らなかったからといって住宅ローンの融資が不利になるようなこともありません。契約する火災保険会社は自分で選択することができます。
住宅ローンを融資するにあたってその金融機関が勧める火災保険に加入することを条件とすることは、保険業法で禁止されている「抱き合わせ販売」にあたるため認められていません。紹介された火災保険にそのまま加入するのが手続き上楽ではありますが、魅力的でない保険会社に申し込む必要はなく、他の火災保険についても選択肢に入れておきましょう。
どの火災保険に加入するかは自由ですが、金融機関より火災保険加入に下記条件が付くこともあります。十分な補償内容で火災保険に契約する上でもポイントとなりますので押さえておきましょう。
ポイント
【金融機関の火災保険契約条件】
- 保険期間が住宅ローン支払期間相当であること
- 建物の評価額以上の補償があること
【住宅ローンと火災保険】
- 契約する火災保険の保険会社は自分で選ぶことができる
- 火災保険の補償開始日は住宅の引き渡し日で契約する
-

火災保険を住宅ローンに組み込む場合のポイントは?
住宅を購入する場合、住宅自体の購入代金のほかにさまざまな費用がかかります。そうした諸費用の中の一つに火災保険があります。火災保険を住宅ローンに組み込む場合のポイ ...続きを見る
保険期間は何年にする?
火災保険は住宅を持っている間は加入しておきたいものです。火災や自然災害のリスクは住宅購入から時間が経っても減るものではありません。しかし、火災保険の保険期間は最長5年です。満期を迎えたらその都度更新していくことになります。
1年契約にして毎年更新していくのと5年の長期契約にするのではそれぞれにメリット・デメリットがあります。1年契約と長期契約のメリット・デメリットと何年契約が多いのかのデータを紹介します。
| 1年契約 | 長期契約 | |
|---|---|---|
| メリット | 補償内容を見直しやすい 1回の支払い負担が軽い | 総支払額が安い 更新の手間が少ない |
| デメリット | 総支払額が多くなる 毎年更新する手間がある | 1回の支払い負担が大きい 補償内容見直しのきっかけが少ない |
1年契約のメリット・デメリット
1年契約には補償内容を見直しやすい、1回の支払い負担が軽いというメリットがあります。1年契約の場合、更新という契約内容を意識するタイミングが毎年やってきます。そこで、「家族が増えて家財が増えたから家財の保険金額を上げよう」だとか「他の保険でも個人賠償責任特約を契約していたから補償を外そう」というような見直しをしやすいです。また、支払う保険料は1年分なので、「何年分もの保険料をまとめて支払うのはきつい…」という場合にも保険料を支払っていけます。
逆にデメリットとしては総支払額が多くなるということがあります。基本的に1年契約を5年繰り返した場合の保険料総額よりも5年契約の保険料の方が安くなります。また、1年契約の場合、毎年毎年更新をしていく必要があります。更新のたびに更新の手続きを忘れてしまった、保険料の支払いができなかったというような契約時のトラブルを抱えるリスクが生じます。
最後に、メリットにもデメリットにもなりうることですが、1年契約の場合は火災保険の改定の影響を受けやすくなります。基本的に改定の影響を受けるのは、それ以後に新規に契約・更新した人です。割引の導入などの良い改定であればメリットとなりますが、保険料の値上げなどであればデメリットとなります。
忙しい入居前は一括見積で効率よく!
長期契約のメリット・デメリット
長期契約のメリットは総支払額が安くなることと更新の手間が少なくなることです。1年契約のデメリットでも説明しましたが、基本的に1年契約を5年間繰り返した場合の保険料総額よりも5年契約の保険料の方が安くなります。1度に大きな金額を支払える金銭的な余裕があるのであれば長期契約で保険料を抑えることを検討してみてもよいでしょう。また、更新の手間が少なくなります。同じ保険会社で継続していくのであれば更新は少ない方が楽でしょう。
デメリットとしては、1回の支払い負担が大きいことと見直しのきっかけが少なくなることが挙げられます。5年分の保険料をまとめて支払うとそこそこ大きな金額となります。大きな金額を1度に支払って、その後の生活が苦しくなってしまわないかよく検討する必要があるでしょう。また、更新という補償内容見直しのきっかけとなるイベントが少なくなります。住環境や家族構成が変わるなどして必要な補償が変わってもそのまま補償内容のまま過ごす可能性が高まります。
そして、1年契約と同様に更新までの期間の長さがメリットとデメリットのどちらにもなり得ます。自分に有利な火災保険の改定があった場合、それの適用を早期に受けるには契約し直す必要があります。逆に不利な改定があった場合は、それの適用を受けるまでの時間を長くすることができます。
保険期間は何年が多い?
最後に、火災保険の保険期間は何年が多いのか、損害保険料率算出機構の「火災保険・地震保険の概況(2024年度版)」より2023年度のデータを紹介します。
| 保険期間 | 件数 |
|---|---|
| 短期(1年未満) | 20,444 |
| 1年 | 2,934,448 |
| 2年 | 2,044,843 |
| 3年 | 294,111 |
| 4年 | 12,314 |
| 5年 | 7,096,112 |
出典:損害保険料率算出機構「火災保険・地震保険の概況(2024年度版)」
年数別にみると5年契約が最も多く、次いで1年契約、2年契約が多くなっています。長期契約で保険料総額が抑えられることや住宅ローンを借りる場合は長期契約を求められることが影響しているのだと思われます。
まとめ
火災保険は住宅の引き渡し日に補償開始日が間に合うように余裕をもって申し込み手続きを行うようにしましょう。また、検討は引き渡し日の1か月半~2か月前から始めるとじっくりと各保険会社の比較や補償内容の吟味をすることができます。見積もりを取る際は一括見積もりサービスを利用すると便利なのでぜひ活用してみましょう。
また、保険期間は1年~5年の中から選ぶことができます。1回当たりの保険料負担、総保険料負担、補償内容の見直しやすさ、更新の手間といった面でそれぞれにメリット・デメリットがあります。保険料総額を抑えたい場合は長期契約が有利ですが、1回で支払う額が大きくなります。どれだけなら支払えるのか、見積もり結果や家計の状況をもとに考えてみましょう。

著者情報
堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。